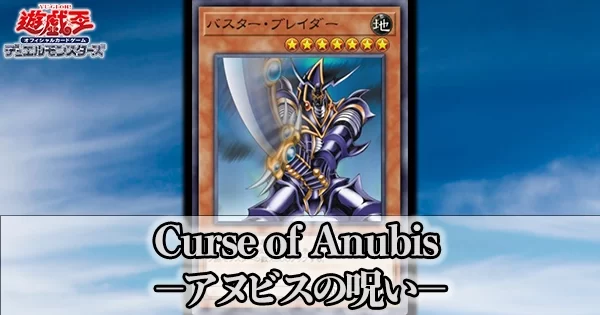遊戯王OCGの2期に収録されたCurse of Anubis -アヌビスの呪い-(カース・オブ・アヌビス)の収録カードと注目ポイントをまとめた記事です。登場当時に注目を集めたテーマやカードを紹介している他、遊戯王の歴史についても触れているので、遊戯王の過去環境を調べる際の参考にしてください。
目次
カース・オブ・アヌビスの登場日
| パック発売日 | 2000年9月28日 |
|---|
| before | after |
|---|---|
| Pharaoh’s Servant -ファラオのしもべ- | Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書- |
カース・オブ・アヌビスの注目ポイント
デッキの基盤が大きく変化したパック
Curse of Anubis -アヌビスの呪い-は多くのデッキに採用されることとなる汎用性の高いカードが多く収録されました。罠カードを封じることができる《人造人間-サイコ・ショッカー》や魔法カードを封じる《王宮の勅命》は汎用性の高さから多くのデッキに採用され、登場からわずか2ヶ月の2000年11月の制限改訂で制限カードに指定されています。
モンスターを墓地へ送る意義が強くなった
墓地からモンスターを特殊召喚できる《早すぎた埋葬》《リビングデッドの呼び声》の登場によって、モンスターを墓地へ送る意味合いが非常に強くなりました。召喚が難しかった上級モンスターを《苦渋の選択》や《天使の施し》で墓地へ送って特殊召喚を狙う戦法が流行します。また、同パックで収録された《人造人間-サイコ・ショッカー》は《リビングデッドの呼び声》と好相性で《サイクロン》や《大嵐》にチェーンをして特殊召喚をすれば完全蘇生が可能でした。
遊戯王の歴史を変えた”刻の封印”登場
相手のドローフェイズをスキップできる《刻の封印》がこのパックで登場。実装当時は使い回すことができず、そこまで注目度はありませんでしたが、2003年2月に登場した《月読命》と《闇の仮面》のループによって一気に凶悪罠カードへ変貌を遂げました。たった3枚で完成するこのループは手札誘発モンスターがなかった当時は打破することが難しくマッチ勝利ができる《ヴィクトリー・ドラゴン》を使用した【TOD(タイムオーバーデス)】デッキが流行しました。
カース・オブ・アヌビスの注目カード
王宮の勅命
魔法カードを封じることができる永続罠カード《王宮の勅命》は登場した当時から、ほとんどのデッキに採用されることになります。毎スタンバイフェイズに維持コスト(LP700)が必要なものの、破壊するタイミングを発動プレイヤーが選択できるためデメリットがほとんどなく、使い勝手が良いカードでした。登場からわずか2ヶ月で準制限、その2ヶ月後には制限となり遊戯王史上始めて禁止カードが指定される2004年3月には禁止カードとなります。
リビングデッドの呼び声
《リビングデッドの呼び声》は《死者蘇生》や《早すぎた埋葬》と異なり、1ターンのラグはあるものの、相手ターンやこちらのバトルフェイズの追撃に使用することが可能です。また、特殊召喚したモンスターが破壊されないければ《リビングデッドの呼び声》自体も破壊されずにフィールドに残るため《ハリケーン》などで使い回すこともできました。墓地に《黒き森のウィッチ》や《クリッター》のような墓地に送られた際に効果を発揮するモンスターが存在していれば、《サイクロン》や《大嵐》の破壊効果にチェーンをして一度特殊召喚をすることでアドバンテージを失わない使い方も可能です。
刻の封印
《刻の封印》は【TOD(タイムオーバーデス)】というデッキタイプを生み出すきっかけとなったカードです。《刻の封印》《月読命》《闇の仮面》の3枚でループが可能となり、相手に何もさせずマッチ単位での勝利を目指すデッキとなっています。
《刻の封印》の登場以降長きに渡りマッチキルが研究されてきましたが、2006年3月には《ヴィクトリー・ドラゴン》と同時に禁止カードとなっています。《刻の封印》が禁止になってからも一定数のユーザーがマッチキルを追い求めてデッキを構築し、【ブラキオンTOD】や【ワールドTOD】など派生デッキが誕生しました。
早すぎた埋葬
《早すぎた埋葬》は《死者蘇生》と比較をすると発動時にLP800のライフコストが必要な点や装備魔法なので破壊される可能性がある点を考慮して登場した当時は下位互換として認識されていました。しかし、《死者蘇生》や《リビングデッドの呼び声》など汎用性の高い蘇生系カードが軒並み規制を受けて、相対的に評価を受けることになります。2002年5月の制限改訂では《早すぎた埋葬》も制限指定を受けています。数年が経過した2008年3月にはシンクロモンスターが登場。《氷結界の龍 ブリューナク》と《早すぎた埋葬》で《レスキューキャット》を使い回す【猫シンクロ】が一気に台頭して2008年9月にはようやく禁止カードに指定されました。
人造人間-サイコ・ショッカー
《人造人間-サイコ・ショッカー》の登場によって、デッキに採用する罠カードの枚数が長期間一定数に抑えられる傾向が顕著に見られました。上級モンスターではありますが、同時に登場した《リビングデッドの呼び声》とのコンボや《モンスターゲート》《名推理》を使用する【推理ゲート】には多く採用されたカードとなっています。また、機械族ということもあり《リミッター解除》や《オーバーロード・フュージョン》の素材など多くの恩恵を受けられるカードとしても活躍しています。
抹殺の使徒
これまで対処することが難しかったリバースモンスターのメタカードとして《抹殺の使徒》が登場しました。《抹殺の使徒》の登場によって《聖なる魔術師》をどのように通すかという読み合いが発生してブラフとして《抹殺の使徒》を発動されても問題ないモンスターを先にセットするプレイングが多く見られるようになりました。リバースモンスターは性質上、起動すると1枚以上のアドバンテージを生み出せるカードが多く、環境が進んだ2009年に大流行した【墓守猫】の対策としても《抹殺の使徒》が多く採用されたこともあります。
砂塵の大竜巻
《砂塵の大竜巻》が登場した当時は《ハーピィの羽根帚》が制限、《大嵐》《サイクロン》ともに無制限といったバック干渉カードが多く、1ターンラグのある《砂塵の大竜巻》はほとんど使用されることはありませんでした。これらのバック破壊カードに大幅な規制が入った後は【ロックバーン】対策などでサイドデッキに採用されることも多くなります。
2006年9月制限に入ると《ダスト・シュート》《マインドクラッシュ》を使用する【ダークゴーズ】が流行し、《マインドクラッシュ》の間接的なメタとしてバック破壊効果を持ちながら、魔法・罠カードをセットできる効果にも注目が集まることになり、採用頻度が高くなってきます。
その後も数少ない汎用バック破壊カードとして多くのデッキに採用されています。
カース・オブ・アヌビスの収録カード一覧
《鉄腕ゴーレム》
《三ツ首のギドー》
《寄生虫パラサイド》
《7カード》
《光の封札剣》
《連鎖破壊》
《刻の封印》
《墓荒らし》
《ホーリー・エルフの祝福》
《真実の眼》
《砂塵の大竜巻》
《リビングデッドの呼び声》
《ソロモンの律法書》
《地殻変動》
《ホーリージャベリン》
《銀幕の鏡壁》
《突風》
《猛吹雪》
《ガラスの鎧》
《世界の平定》
《魔法探査の石版》
《金属探知器》
《白衣の天使》
《便乗》
《強制接収》
《DNA改造手術》
《一族の掟》
《補充要員》
《大騒動》
《停戦協定》
《聖なる輝き》
《正々堂々》
《王宮の勅命》
《マジカルシルクハット》
《抹殺の使徒》
《撲滅の使徒》
《浅すぎた墓穴》
《早すぎた埋葬》
《検閲》
《禁止令》
《カオスポッド》
《フレイムキラー》
《ビッグバンドラゴン》
《バーニングソルジャー》
《ミスターボルケーノ》
《炎の剣豪》
《精神寄生体》
《メカファルコン》
《メカファルコン》
《バードマン》
《バスター・ブレイダー》